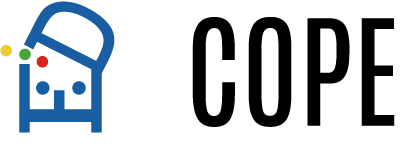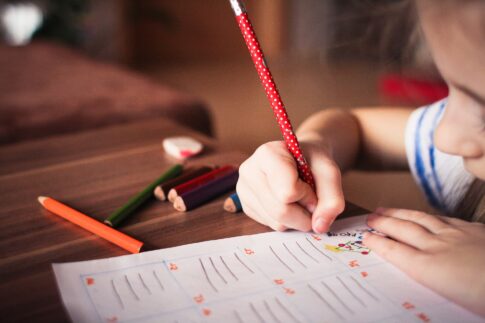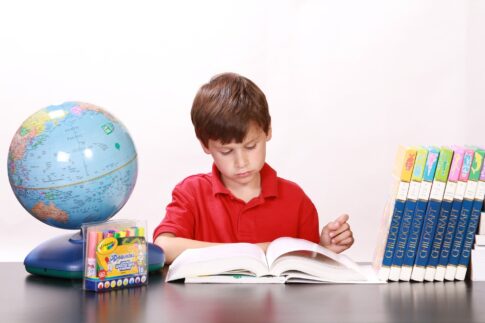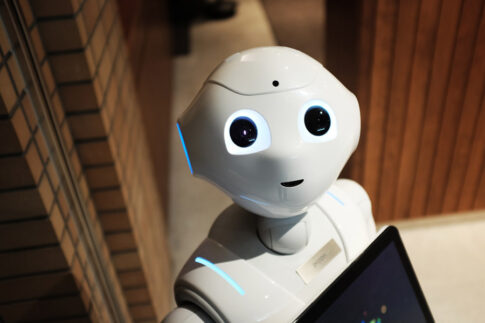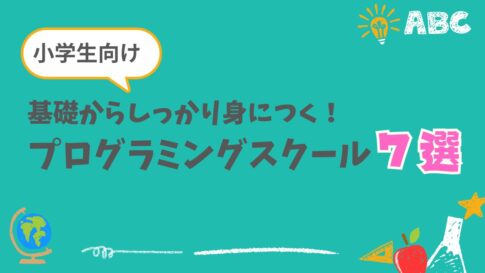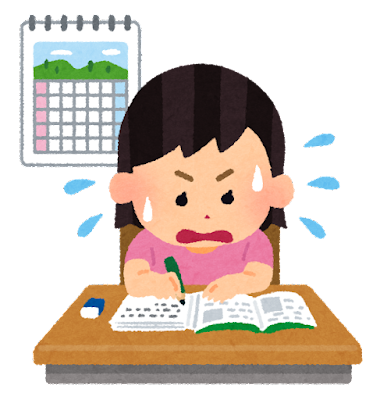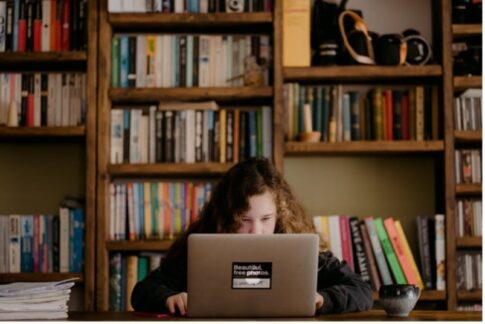みなさん「アンプラグド」という言葉をご存知ですか?直訳すると「プラグを抜いた」という意味で、もともとはピアノやドラムセットなど、電子装置を使用しない楽器を使った演奏スタイルのことをそう呼んでいました。
この言葉をなぜ今取り上げたかというと、音楽の世界だけでなくプログラミング教育の世界でも「アンプラグド」という言葉が使われるようになってきたからです。
プログラミング教育の世界で使われる「アンプラグド」は、パソコンやタブレットなどを使わずに、アナログな方法のみでプログラミング的思考力やコンピューターサイエンスの考え方を学ぶことを指します。
「アンプラグド」が使われるようになった理由
特に日本では「アンプラグド」という言葉が最近使われ出しましたが、その理由として2020年から始まる小学校プログラミング教育の必修化があります。
実際に小学生にプログラミングを教えようとするときの方法は主に三つです。一つ目は「Scrach」などのソフトを使って教えるプログラミング。二つ目はロボットやドローンなどのハードを使って教えるプログラミング。そして三つ目に、一切コンピュータを使わないアンプラグドで教えるプログラミングです。
この三つのうちアンプラグドで教える利点は、初めてプログラミングに触れる人や低学年の子ども達にとっても敷居が低いところです。特に小学生はパソコンを使った経験も少なく、家庭の方針によってはタブレットに触れた経験が少ない子も多々います。そのような子ども達には電子機器を使わずにコンピュータの仕組みを教えられるアンプラグドは最適です。
また教えるほうも学ぶほうもプログラミングの経験が浅い場合、いきなりソフトを使うと本質的な考え方よりもかたちや方法が先行してしまう場合があります。そういった意味でもアンプラグドの勉強方法はコンピューターサイエンスのベースとなる考え方が身につくので理想的です。
ただし、プログラミング教育においてアンプラグドだけで良いかというとそうではありません。
アンプラグドはどこまでいってもベースとなる考え方を学ぶだけで、プログラミング言語によるものづくりはできません。コンピュータがどのように指示を聞いて動いているか、その考え方を理解することはとても大事です。先にアンプラグドで思考する力を身に付けていった後に、実際のコンピュータを使ってプログラミングを勉強していくのが順番としては正しいかと思います。
2020年の必修化によってアンプラグドでプログラミングを教える授業が確実に増えてきますので、今回の記事でアンプラグドについて知っていただければ幸いです。
参考
アンプラグド「だけ」ではプログラミング教育をやったことにならない
https://edtechzine.jp/article/detail/1637